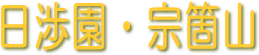
日渉園・宗箇山 ~紅葉の仕組み~
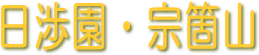 |
【広島市西区 平成14年11月17日(日)】
11月の定例観察会は広島市街を見下ろす宗箇山とそのふもとにある日渉園です。テーマは「紅葉の仕組み」
まず日渉園と宗箇山についてちょっと説明を。
日渉園
江戸中期、広島藩の藩医後藤松眠が三滝の地に開いた薬草園です。当時の医者は治療に必要な薬草を自宅の周囲に栽培するのが普通だったそうで、今でいうキッチンガーデンのような感覚だったのでしょう。松眠の子後藤松軒は蘭学を学び、シーボルトにも師事し高野長英とも親交があったそうで、その後幕府から追われることとなった長英をこの日渉園に一時かくまったこともあったそうです。現存する藩立薬草園は全国でこの日渉園だけ。現在は広島大学が管理しています。
宗箇山
標高356m。広島市街の西に位置し、ふもとまで住宅街が広がっています。江戸初期、広島藩主となった浅野長晟と共に入国した武将上田宗箇の名を冠した山です。宗箇は茶人でもあり、城下に造営した茶室の借景としてこの山の頂に巨大な松を植えたそうです。この松は「宗箇松」として親しまれ、山自体も宗箇山と呼ばれるようになったそうです。今では市民の手頃なハイキングコースとなっていますが、オーバーユースによる登山道の荒廃がちょっと気になります。
以上、勉強の時間終了です。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
11月も半ばになると朝はぐっと冷え込みます。特に今日のような晴れた朝は。
紅葉のピークはやや過ぎたとはいえ、ここ三滝には紅葉の名所「三滝寺」もあり、70名を超える参加者が集まりました。
| 朝日の中でオープニング |
緑色の葉がなぜ赤色や黄色になるのか。落葉樹の葉はなぜ秋に落ちるのか。紅葉する葉が赤いのは表の面だけなのはなぜなのか。いくつかのお題が示されました。
| 神田先生 |
日渉園内の解説は広島大学医学部附属薬用植物園の神田先生です。ダジャレも織り交ぜたお話で、難しい話も楽しく聞くことができました。
| イセハナビ |
体が少し温まってきたところで、次に宗箇山を目指しました。途中に通る三滝寺のモミジが朝日に照らされてすばらしいこと。
登山道には様々な落ち葉が散らばっています。頂上でのネイチャーゲーム用にいくつか拝借。紅葉のことについてもああだこうだと話をしながら登っていきます。
| 宗箇山 |
だんだん暑くなってきました。尾根筋に出ると宗箇山の山頂も見えてきます。
この頃すでに隊列は伸びてしまい、小グループごとに観察しながらノッコノッコと登っていきました。
| 山頂で昼食 |
そしてちょうど12時に到着。まずは昼食をとりました。
山頂からは南方向の展望が開けていて、広島市街が一望できます。あぁ、気持ちいいぞ。
| 広島市街 |
昼食後は、拾った落ち葉を使ってひとつアートでも…。芸術の秋ですから。
| 金魚です。オオサンショウウオ ではありません、念のため。 |
そして、今日のリーダーの舛田さんから、紅葉の仕組みについてレクチャーがありました。
冬が寒く乾燥する地域には落葉広葉樹が多く分布しています(地球規模で見て)。雪が降っても地面は以外と乾燥しています。葉からの水分蒸散を押さえて”脱水症状”になるのを防ぐために、冬の前に葉を落とし身を守っているのだそうです。
落葉する前に色が変わる仕組みはその色によって違うのですが、ごくおおざっぱに言うとこうです。
《赤色の場合》①葉緑体に含まれるクロロフィル(緑色色素)が壊れる。②葉の付け根にシャッターができて光合成で作った糖が葉に貯まっていき、その糖に含まれるアントシアン(主に赤色色素)の色が目立つ。※茶色の場合はアントシアンに代わってフロバフェンという色素が働きます。
《黄色の場合》①は同じ。②もともと葉にあったカロチノイド(主に黄色色素)が結果として目立つ。
| やさしい語り口の 舛田指導員 |
これで紅葉の仕組みや冬を迎える植物の工夫もよく分かりました。納得です。そして舛田さんは最後をこう締めくくりました。
自然観察会は手段であって目的ではない。観察会を通じて自然をより深く理解し、その理解を自然保護に繋げていってほしいと。本当にそのとおりです。自分自身、心にピン留めしておかなければならない言葉でした。
とはいえ、デートで紅葉狩りに行って「アントシアンが…、カロチノイドが…」なんて言い出すのはやめておきましょう。情緒に欠けますからね。
下山途中に、枯れ木の幹にびっしりと生えているキノコを見かけました。彼らがいるおかげで、森が倒木や落ち葉であふれかえることがないのです。この木もいずれ彼らに分解されます。
植物は無機物から有機物を作り、植物自身や動物がそれを利用する。そして枯れたり死んだりした後は微生物や菌類などが二酸化炭素やアンモニア、水などの無機物に分解する。そしてまたその無機物を植物が取り込む。見事に完結した循環ですね。