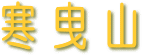
寒曳山 〜秋の草原で何思う〜
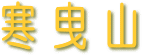 |
【広島県大朝町 平成16年9月19日(日)】
日中の暑さも少しずつ和らぎ、それに伴って朝夕の涼しさが増してきました。野山にはいつのまにか秋の七草が揺れています。
”萩が花 尾花 葛花 撫子の花 女郎花 また藤袴 朝顔の花 ” (山上憶良)
この歌が詠まれた万葉の時代、人々は季節の移り変わりを、現代人よりもずっと敏感に感じ取っていたでしょう。
花だけでなく、渡り鳥や虫の声、月の満ち欠け、風や水の温かさ冷たさなど、日々刻々と変化していく自然を見つめ、その変化に心を動かし、歌に詠み、旬を味わい、そんな自然の中で日々暮らしていくことを楽しんでいたのではないでしょうか。
当時は、現代人が考えるほど退屈な暮らしではなかったのかもしれません。
9月の定例観察会用に作った資料の表紙には、そんなことを考えながら秋の七草の写真を配してみました。
今回のテーマは「秋の草原で感じるものは?」 担当はワタクシ、yamanekoです。
午前7時、広島駅新幹線口でマイクロバスに乗車する方々を待ちます。今回はバスの添乗員も兼ねているので、乗車予定のリストでチェックして、そろったところで出発。ちょうど8時でした。
あいにくの雨模様ですが、天気予報は回復を告げています。
ほどなく雨は上がり、現地に到着したときには薄日も差していました。
| 開会の様子 |
開会に先立って、まずスタッフに集まってもらい簡単な打ち合わせを行いました。
今回のコース確認とグループ分け(参加者5〜6人にスタッフ2人程度で一つのグループ)。そして、参加者が主体的に観察をし、自らの発見を皆で楽しむことができるよう、「教える側、教えられる側」といった構図を作らないようお願いしました。スタッフはあくまで疑問や発見を掘り起こすきっかけ作りに務め、あとは自分のグループの安全管理、時間管理に意を用いてもらおうということです。
あと、どのグループにも属さず、観察会の運営全体をチェックする役割の者を2人。これは加藤代表とyamanekoです。
9時30分、予定どおり開会。参加者、スタッフ合わせてちょうど50人でした。
加藤代表から、先日の台風18号の話題に関連して、海水表面の温度の上昇、地球規模の温暖化についての話がありました。また、前回の観察会で発見され話題になった「バッタの孤独死」の謎について、その後もその疑問を解消すべくあれこれと調べて自分なりの答えを出された方の話を紹介されました。このような方がおられるということは観察会を企画する側としてもうれしい限りです。
次に担当からのお知らせとして、今回は「要所要所で参加者を集めて解説をする」といったやり方はしない。スタッフが説明するのを待っていないで、自分の疑問や発見をどんどん口にして周りの人に話しかけてみて。また、話しかけられた人も周りと一緒になって考えて楽しんでほしい。気楽に仲間うちで観察して歩くつもりで、自分で見つける喜びを感じてもらいたい。といった趣旨のことをお話ししました。
とはいっても、「詳しく植物の名前を教えてほしかったのに…。」という方もいるかもしれません。
そこで、一週間前の下見のときに見かけた生き物をエリア別にまとめて資料に列挙しておきました。今日は自分の目でしっかり見ておいて、帰ってからこの資料を使って調べることができるようにしておいたのです。何の手がかりもないまま調べるよりも、ずいぶん楽に調べられるはずです。
簡単なストレッチを終え、なんだかんだで出発したのは10時。
往路はゲレンデ横に広がる森の中の「林間エリア」を登っていきます。
| 「こりゃ何だ?」 |
夜半まで降っていた雨のせいで足下が滑りやすくなっています。でも、グループごとにスタッフがうまくリードして、狭い登山道で渋滞することなく観察していました。
早くもあちこちで笑いや「おおーっ」といった驚きの声があがっています。小さな観察会があちこちで開催されている形で、当初考えていたとおりの進行です。
| スギヒラタケ |
チゴユリが茎の先端に黒い実を一つ付けていました。あるグループではそれを囲んでみんなでワイワイやっています。
チゴユリの実は誰が運ぶのか? 「鳥じゃないか?」、「黒くて目立たないし、こんな林の下まで鳥は来ないんじゃないか。」、「じゃあ虫か?アリが運ぶんじゃないのか?」、「自分で落ちて転がって行くんじゃないか? 丸いし。」、「地面は枯れ葉だらけで転がらんじゃろ。」、「地下茎で増えるのかも。」、「じゃあたくさんのエネルギーを使って実を結ぶ理由は?」 みんなで盛り上がっています。
| あれは何? どれどれ? |
登りはじめはヒノキの林だったのですが、途中からミズナラ、ナナカマド、コシアブラなのど落葉樹の林に変わってきました。林床も少し明るく感じます。
| 林間エリアの道 |
だんだん傾斜がきつくなってきました。汗がにじんできますが、ときどき涼しい風が林の中を抜けていくので辛くはありません。でもこれから先、特に山頂直下はもっと急になってきます。
途中、ソヨゴの木が打ち付けられた看板をくわえていました。長い時間をかけて樹皮が看板を巻き込んだのです。
でも待てよ。よーく見ると巻き込んでいるのは上の部分だけであって、下の部分は何ともなっていません。なんで?
下から登ってくるグループがここを通りかかるたびにこの疑問をぶつけてみました。
なるほどと唸るものから大爆笑するものまで、さまざまな説が飛び出しましたが、これにもちゃんと理由があるのだそうです。
| 山頂エリアの道 |
山頂直下のきつい坂をクリアすると山頂の尾根筋に出ます。急に展望が開けました。「天狗岩」の上に上がって小休止。胸がすくような景色です。ああ風が涼しい。
ここから三角点のある山頂まで、ほとんど高低差のない「山頂エリア」を歩きます。明るい尾根道です。
クロモジの木に何やらつぼみのようなものが。でも何で今頃?
これはつぼみではなく虫コブなのだそうです。だったら中を見てみよう。「いただきます。」と断って虫コブを一ついただきました。そしてナイフで切ってみると…、いました、いました。虫が。確かに虫コブでした。
それにしてもこの虫は一生をこの中で過ごすのでしょうか。それともいずれ外の世界に飛び出すのでしょうか。
| 山頂 |
11時50分、最初のグループが山頂に到着。後続も次々と上がってきました。
早速、弁当を広げます。日が差すとジリジリと暑いくらいですが、雲がそれを遮って風が汗を冷やすと、急にエアコンの効いた部屋に入ったときのように気持ちいい。
| 山頂から南方向 |
| 山頂から北方向 |
山頂にはたくさんのトンボ(アキアカネ?)がまさに”乱舞”していました。これだけの数のトンボが集まるのは、それなりの数のエサとなる蚊などの虫がいるということでしょう。トンボにしてみれば食べ放題のバイキングです。でも、そのトンボを狙ってツバメもやって来ていました。彼らも渡りの前の栄養補給でしょうか。
| ヒトヨタケ |
午後1時、山頂を出発して再びグループごとに動き出します。
復路はゲレンデの「草原エリア」を下っていくことになります。ここからは「林間エリア」や「山頂エリア」とはまた異なった自然が見られるでしょう。
| 草原エリア |
草原を下りながら辺りの山並みを眺めると、同じような高さの稜線が延々と続いているのに気づきます。この風景は、例えば中部山岳や北関東のギザギザの山並みとは明らかに異なったものです。
今から約2千万年前(恐竜は遙か昔に絶滅し、人類の出現にはまだ間がある頃)、この辺りの地形は浸食が最終段階まで進み平原状になっていたといいます。それがじんわり隆起してきて標高1,000mくらいの高原状になり、また新たに浸食を始めたのです。これからもどんどん谷を刻み、やがて険しい山脈を形作る頃がくるでしょう。そしてまた浸食しつくすと平原状になるのです。気の遠くなるような時間をかけて。大地の輪廻です。
| ホクチアザミ |
草原エリアを下るうち、秋の七草のうち5つを見かけました。目にしなかったのはクズとフジバカマです。自生するフジバカマは今ではほとんど見ることができません。なのでこれはしょうがないとして、どこにでもはびこっているクズを見かけなかったとは。意外でした。標高のせいでしょうか。
| ゲレンデ越しの寒曳山 |
2時30分、スタート地点の駐車場に戻ってきました。爽やかな草原の風に吹かれて汗も引いています。
参加者の無事を確認してから、最後のまとめです。
今回の観察会はあえて教養講座的なものとはしませんでした。参加者の皆さんはどのように感じたでしょうか。物足りないと感じた方もいたかもしれません。
しかし、私たちNACS−Jの自然観察指導員が行う観察会は、知識を学ぶのではなく、自然の中から新しい発見をすることを目的としたものなのです。
スタッフは安全確認や進行確認のため観察会の1週間前に必ず下見を行います。でも実をいうとこの下見が一番楽しかったりします。何故なのか? それは、誰が先生でもなく生徒でもなく、気がついた人が疑問を口にし、皆がワイワイ寄ってきて、あーでもない、こーでもないと。その過程でさまざまな発見をしたりします。とんでもない意見も出ます。結論が出ないことも多いです。でも、後日なんかの拍子に答えが見つかったりすると、その喜びは印象深く長く心に残ります。こんな楽しみを参加者の皆さんにも感じてほしい。それがこの観察会の意図だったのです。(もちろん、最終的な目的はさらにその先にあって、”こんな楽しみを与えてくれるこの身近な自然を、壊されたくない、守っていきたい、未来に残していきたい” そんな気持ちを持ってもらう。それがNACS−Jの腕章をして観察会を行う場合の目的なのであり、その手段としての観察会なのです。)
午後3時、予定どおり閉会です。
準備開始から3ヶ月、天候にも恵まれ、けが人もなく、無事終了することができました。
協力していただいたスタッフの方々に心から感謝です。
山上憶良が秋の七草を詠んでから約千3百年。今に生きる我々はそれらの花を目にすることができ、同じように季節の移り変わりを感じることができた。さて、今から千3百年後、そのころの野山はどうなっているだろうか。人々は秋の七草を楽しむことはできるのだろうか。