
伊豆ヶ岳 〜秩父の玄関口を歩く〜
 |
【埼玉県 飯能市 平成19年9月15日(土)】
今年の秋はカレンダーの並びが良く、3連休がいくつもあります。今日はその第一弾のその初日。天気予報も晴れマークだし、やっぱり野山に行くしかないでしょう。
今回はめずらしく電車で移動することにしました。午前8時、池袋駅は平日の3割減といった混雑度。JRから西武線のホームに向かいます。yamanekoは今から13、4年前に通勤で西武池袋線を使っていました。沿線に女子大が多いので平日は若い学生が多く乗り込んできますが、この路線が秩父につながっていることもあって、休日の朝はむしろ山歩きの格好をした人(もっぱら中高年)が目立ちます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
8時15分、発車のベルに押されて飛び乗ったのは飯能行きの急行。これだと終点の飯能で秩父行きに乗り換えなければなりません(次発の電車は秩父直通でした。残念。)。急行なので所沢までに停まる駅は石神井公園とひばりヶ丘のみ。所沢から先は各駅に停まります。
9時6分、飯能に到着。下りたホームの向かい側で9時21分発の三峰口・長瀞行きを待ちました。飯能を過ぎると一気に山里風景になってきます。
| 正丸駅 |
9時56分、正丸駅到着。思ったより下りる人が少なかったのが意外でした。正丸から伊豆ヶ岳を通って子の権現(ねのごんげん)へ抜ける縦走コースは人気の道で、多くのガイドブックにも紹介されています。なのにここで下りる人が少ないというのは、縦走には5、6時間はかかるので、すでにみな出発していると考えるのが妥当でしょう。何か出遅れた感満点ですが、当方、今日もゆっくり歩きなので、縦走をせずに伊豆ヶ岳の往復を考えています。とりあえず駅のベンチに腰かけ、持参したカレーパンで腹ごしらえです。
| 出発地点 |
ストレッチを済ませてリュックを背負っていたら、もう次の電車がやってきました。
10時15分、ようやく出発です。まずは駅の脇にある表示に従って階段を下りていき、線路の下のトンネルをくぐって山手の方角に向かいます。
| 渓流 |
登山コースに設定されている谷筋は左右に山が迫り、渓流と車道とそれに沿って点在する民家の他には広々とした土地はありません。大水が出たら一気に濁流が流れ下るのではないかといった感じの場所です。
川からは心地よい水の音。キセキレイが尻尾を上下させながら流れの中の岩を伝っていました。
| ゲンノショウコ | キツリフネ |
川岸にはゲンノショウコやキツリフネなどの花が見えます。あと、ノブキの白い花、ミズヒキの紅い小さな花、ハキダメギクやイヌガラシも。雑草とひとまとめに称されるこれらの花も、ルーペ一つでビックリするほど華麗な姿に変身するのを知ってますか。驚きの世界ですよ。
| 秋の味覚 |
民家の庭先に大きく実った栗。食べ頃までにはもう一月くらいはありそうですが、秋を感じる風景です。
| ヒガンバナ |
河原にヒガンバナが。もうそんな季節か。それにしてももうじき彼岸の入りとは思えないほどの今年の暑さです。「暑さ寒さも彼岸まで」と言いますが、服を着た状態で心地よいのはだいたい18度前後。この時期、例年最高気温はまだ27度くらいありますが、最低気温は18度くらいになります。日中はまだ残暑のさ中でも朝夕が過ごしやすくなったことで涼しさを感じ、秋の訪れを知る、ということなのだそうです。しかし、今年の場合、本当に彼岸を過ぎると涼しくなってくれるのでしょうか。
| 安産地蔵尊 |
道の脇に小さなお堂がありました。解説板を読むと「安産地蔵尊」とあります。明治のはじめ頃、このお地蔵さんを移転させようとした際、急にその重量が増して動かせなくなり、以来ここのお堂に安置されているとのこと。地域の皆さんが大切にお祀りしているおかげで、未だにこの地域ではお産で命を落とす人はいないということです。
| ツユクサ |
このツユクサも花期の長い花です。花自体は一日花で、その日のうちにしぼんでしまいますが、初夏から秋にかけて次々と咲いていきます。この花を搾り汁を友禅染の柄の下絵を描くのに使っていたというのはよく知られた話。これで描いた下絵はあとで濯ぐときれいに消えてしまうのだそうです。
さっきから霧雨のような雨がぱらついているのに、上空の雲に雨雲のような暗さはありません。それどころかときおり薄陽が差しています。上り坂でほてった腕に霧雨が気持ちよく感じられます。
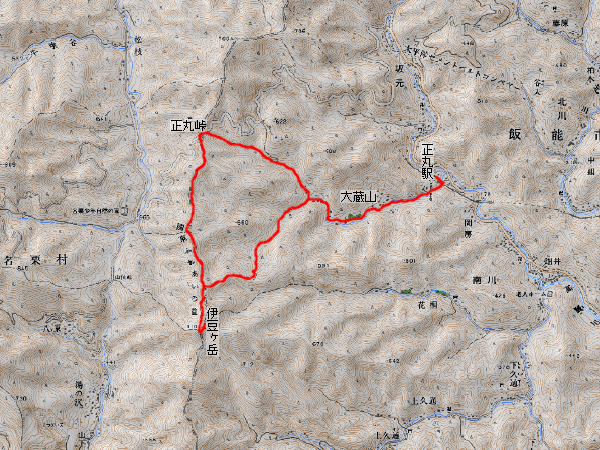 Kashmir 3D |
10時50分、分かれ道に到着しました。左に行くと伊豆ヶ岳への近道ですが、おそらく険しい道でしょう。右に行くと正丸峠を経由して、稜線沿いに伊豆ヶ岳へ向かう道。帰りに左の近道を通って帰ってくることとして、往きはここを右にとって正丸峠を目指すことにします。
| 馬頭観音の分岐点 |
二又の真ん中にある馬頭観音に手を合わせて再び歩き出します。
| ダンコウバイ |
ダンコウバイが実を付けていました。中にはすでに紅黒く色づきはじめているものもあります。一つ採って臭いをかいでみたらクスノキ科の植物だけあって薬くさい。さすがに囓ってみる気にはなりませんでした。春まだ浅い頃、枝中に黄色い小さな花をちりばめて咲いていたであろうこのダンコウバイも、こうやって実を付け、あとは鮮やかな黄葉で季節を締めくくるのみです。
| 山道へ |
ルートは山道となり、少しずつ狭く、きつく、また足場も悪くなっていきます。今週は雨が多かったからか山道を水が流れているところもありました。というか、川底を歩いているといった方が正確かもしれません。また、台風9号の爪痕でしょう、川沿いに倒木が目立っていました。
| 山の神 |
鬱蒼とした森の中に佇む小さな祠。毎年2月の初申(はつさる)の日に山の神をお祀りするのが「お申講」で、山の多い飯能では盛んに行われているのだそうです。山の木々を守り、そこに分け入って働く人々を守ってくれる大きな力。そこに神の存在を認め、それに祈ろうという気持ちは自然に生じてくるものでしょう。大きな自然の中では人間は謙虚になるものですよね。
日本中、どんなところにも必ずこういったお堂などがあります。地域によって若干の差はありますが、自然信仰を基本としたその土着の風俗習慣は日本人の精神的な基盤として脈々と受け継がれているのだと思います。しかし、現代の日常生活ではあまり顧みられることのなくなったこういった地域の文化遺跡。昔は日々の暮らしの中で重要な位置を占めていて、いわば地域の社会にとって求心力的な存在であったのでしょうが、これをこれからも後世につないでいくことはできるでしょうか。
谷筋をさかのぼるにつれ道はどんどん険しくなっていきます。特に、沢の流れが途切れたところにある、正丸峠を頭上に望む最後の斜面は、強烈な階段の直登になっていて息も絶え絶えに登っていくことになりました。
| 奥村茶屋 |
そして峠にたどり着いたらこの風景。この峠の茶屋の裏手にある深い谷をまっすぐ登ってきたことになります。表に出てみるとアスファルトの林道が通っていて、「正丸峠」という簡素なモニュメントが建っていました。深い森や険しい道を登ってきたので、ちょっと気が抜けます。
| 山並みのグラデーション |
茶屋の隣は展望台になっていて、さっきまで登ってきた谷が目の前にありました。少しずつ色合いを淡くしていく山並みのその先に、遠く街並みが見て取れます。地図とコンパスで確認してみると、狭山市や所沢市あたり。うっすらと西武ドームも確認できました。
正丸峠で10分ほど休憩し、11時35分、再び歩き始めます。
| 尾根筋の道 |
ここからは尾根筋の道。稜線を越えていく風が涼しく、木々も少しまばらで、明るい雰囲気です。アップダウンはあるものの、正丸峠までの登り一辺倒の山道とは異なり非常に楽です。
11時50分、標高720mの小高山を通過。2万5千分の1の地図には記されていませんが、立てられた標識がその名を教えてくれます。
| 杉林 |
この辺りの杉林は下草も刈られ間伐もなされているようです。木漏れ日の中の山歩き。心身がリフレッシュされていくのが分かるようです。
| 男坂 |
12時5分、伊豆ヶ岳の山頂直下にある男坂までやってきました。滑りやすい急な坂で、上り口にはロープが張られ遮られています。ここから右手に女坂という傾斜の緩い上り道が山頂を巻くように付いていますが、山頂まで10分くらいはかかります。ロープをまたいで男坂を登る人も多いようで、横の看板には「自己責任で…(云々)」との注意書きがありました。yamanekoはというと、当然、女坂です。ハイ。
| カシワバハグマ | キバナアキギリ |
女坂の方もどうしてこれが結構な坂道でした。ついつい足元ばかり見て黙々と登ってしまいがちですが、ところどころに咲く花々が足を止めるきっかけを作ってくれて、助かりました。
| ヤマジノホトトギス | アキチョウジ |
野山には秋の花が増えてきました。下界はまだ残暑のまっただ中ですが、やっぱり少しずつ季節は移ろっているんですね。
| あとわずか |
前方の坂の上に青空が。頂上がすぐそこにあります。
| 山頂 |
12時20分、ようやく山頂(851m)に到着しました。正丸駅が標高300mだったので、約550mほど上ったことになります。数字以上に厳しかったように感じたのは、日頃の不摂生のせいでしょうか。
| 武川岳 |
山頂は木々に囲まれあまり展望はききません(冬になって木々が葉を落とせばまた違うかもしれませんが。)。唯一、北西の方角に展望が開けていて、正面に武川岳(1052m)の姿を望むことができました。その奥にちょこんと山頂をのぞかせているのが武甲山(1304m)です。
| 広場 |
山頂から一段下がったところに広場があったので、ここで昼食をとることに。ごつごつとした大きな岩がベンチ代わりです。
秩父といえば「秩父セメント」で有名なように、石灰岩が多く見られる山地です。今から約2億年前、日本全体(後に日本列島ができるあたり)は海の底に沈んでいて陸地はなかったといいます。海底には砂や泥が堆積し、サンゴなどの生きものが生息していて(当時は暖かい海だったのか?)、その膨大な死骸が沈殿しかたまったものが石灰岩です。また、放散虫という生物の殻(珪酸質)が積もってできたのがチャートで、この伊豆ヶ岳はチャートでできているそうです。チャートは硬い岩石で、浸食に強いため、ごつごつとした山容を形作るのだそうです。このあたりの地層は「秩父古生層」と呼ばれ、やがて古生代の終わりか中生代(諸説有り)に至って陸上に顔を出し秩父山地となったということです。(その後、新生代第三期(6500万年前〜1800万年前)にも浅い海になっていた時期があるとのことです。)
しかし、どえらいものの上に座って昼メシを食べていたものです。
| 崖のような斜面 |
昼メシを終えて、地図などを眺めながらぼんやり。十分にくつろいだ後、下山を開始します。時刻は午後1時です。
帰りは正丸峠を経由せず、馬頭観音の分岐点に直に下りていく近道のコースです。
上の写真はそのコースの途中にあった崖のような斜面で、短いトラロープが垂れ下がっているのみ。それをつたって約50mをジワジワ下りていくのですが、しりもちをつくのならまだしも、下手をしたら頭から転がり落ちてしまいそうなほどの傾斜でした。
| 沢筋へ |
1時30分、ようやく沢筋に下りてきました。ここから先も山道らしいものはあるものの、ほとんど川の中を歩いているような感じ。しばらく岩を乗り越えたり川を渡ったりしながら、ようやく道らしき様相を呈して来たのは分かれ道の直前あたり。想像以上にハードな下山路でした。
| 分かれ道 |
1時45分、馬頭観音の分かれ道のところまで帰ってきました。上の写真の奥から下りてきたのですが、この心地よさそうな林間の道に見えるのはここから見える範囲くらいもの。その先は油断は禁物です。
2時5分、正丸駅に到着。しかし今日は暑かった。吸湿速乾性のウエァを着ていましたが、その機能をはるかに上回る発汗量でした。時刻表を見ると次の電車は20分後。売店の缶ビールで喉を潤すのにちょうどよい時間です。(今日は車ではないのでこれができるのです。ヤッホー!)
午後4時、池袋駅はそろそろ夕方の混雑を見せ始めていました。パンパンに張ったふくらはぎを庇いながら地下通路を歩きJRのホームへ。たまには電車での移動もよいものです。