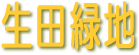
生田緑地 ~開発の中に残った緑地~
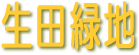 |
【川崎市 多摩区 平成18年5月21日(日)】
この週末は久しぶりに晴天。輝くような青空を見ると、もちろん家でじっとしてなんかいられません。
今日はNACOT(自然観察指導員東京連絡会)のHPで告知されていた「道草倶楽部」という小さな観察会に参加してみようと思い、妻と二人で出かけてみました。
場所は多摩川を渡った向こう、川崎市多摩区にある生田緑地です。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 小田急 向ヶ丘遊園駅 |
新宿駅を9時31分発の小田急線に乗って、最寄りの向ヶ丘遊園駅に着いたのは9時52分。所要時間はわずか21分です。
駅前で「道草倶楽部」を主催する柿沼さんと合流。柿沼さんはNACS-J(日本自然保護協会)の自然観察指導員。もちろん初対面ですが左腕の緑の腕章ですぐに分かりました。集まったのは全部で6人。後からもう一人合流するとのことで、総勢7名の観察会です。
| 線路沿いの道を行く |
線路沿いの道を通って生田緑地へ向かいます。生田緑地はなだらかな起伏の多摩丘陵の一部で、クヌギやコナラの自然林が残る憩いの場所です。周囲は市街地として早くから開発され、今では都市の中に取り残されたオアシスのようなところです。園内には日本民家園や青少年科学館、岡本太郎美術館などがあり都市公園の様相を呈していますが、それでも自然の姿を多く残しています。ここにはまだ子供が小学校低学年の頃、2、3度訪れたことがあります。当時はまだ隣接する向ヶ丘遊園地が営業していました。(今は閉鎖されてしまって、小田急の駅にその名を残すのみです。)
| 北野神社 |
途中にある北野神社という小さな神社に寄ってみました。古くは韋駄天社と呼ばれていたそうです。ウグイスのさえずりがすぐ近くから聞こえてきました。木陰に入ると明らかに気温が低く涼しく感じます。風もそよそよと吹いてきて心地よい散歩です。
サンショウの木があり1枚葉をいただいてみるとあの良い香りがしました。イヌザンショウにはこんな芳香はありません。もしかしたら民家の庭先から逃げてきたものなのかもしれません。
| ガマズミ |
境内の端にガマズミが白い花を咲かせていました。スイカズラ科の落葉低木です。清新なイメージのする花ですが、臭いはあまりよくなく、その臭いで虫を呼び寄せるのだそうです。
| クサノオウ |
社叢を離れて再び民家の間の道を行きます。道ばたにクサノオウがたくさん咲いていました。ケシ科の植物で、茎を切ると黄色の乳液が出てきます。これには有毒成分があり、またそれを薬としても利用していたのだそうです。名の由来は黄色い汁から「草の黄」という説や有用な薬草だったことから「草の王」という説などがあるそうです。
スイカズラの花ややクサギの若葉など、道ばたにある植物を観察しながら歩いていくと、ほどなく生田緑地に到着しました。
| 北西側の入り口 |
生田緑地には東口、西口、北口がありますが、それ以外にもいくつか小さな入り口があるようで、ここも北西側にある住宅地に隣接した小さな入り口です。
| 東屋 |
木漏れ日が気持ちいい。我々以外にも散策している人がチラホラいました。
サクラの幹に丸い穴が開けられていました。まだ生きている木なのでこの穴を開けたのはコゲラではないようです。生息場所からしてアカゲラではないので、アオゲラではないかということになりました。確かにアオゲラは多摩丘陵でよく見かける鳥です。
| トサシモツケとベニカミキリ |
むせかえるような花の香りがしてきました。見ると満開のトサシモツケに小型の甲虫が群がっています。なかでも鮮やかな紅色のベニカミキリ。陽光に輝いてルビーのようでした。それにしてもこんなに目立つ色をしていると鳥の餌食になりやすいのではないでしょうか。鳥の色覚は人間をはるかに上回るといいますから。
ところでベニカミキリの幼虫は竹の害虫だそうです。場合によっては使えそうですね。
| ツメクサ |
足下には小さな小さな白い花。ナデシコ科のツメクサです。細い葉が鳥の爪のようだということで名が付いたのだそうです。花の直径は約5㎜ほど。こんな小さな花にも訪れてくれる虫がいることに、あらためて驚きを感じます。
| 谷戸 |
里山の山ひだの最奥、谷戸(やと)とかヤチとか呼ばれる地形の場所です。湿潤な環境が多くの生命を育んでいます。
| アカスジキンカメムシの脱皮 |
アカスジキンカメムシの脱皮に遭遇しました。下の黒っぽいのが脱け殻。細い足の部分まできれいに残っています。抜け出るときの体や足は見た目より柔らかいのかもしれません。でなければあんなにきれいな殻を残して抜け出ることはできないのではないでしょうか。どの昆虫も脱皮直後は動きも鈍く鳥などに捕食されやすいといいます。この危険なときをくぐり抜けることができたら、ほどなく色鮮やかな模様の成虫になるでしょう。
| オカタツナミソウ | フタリシズカ |
林の縁にはオカタツナミソウやフタリシズカなど、地味ながらも愛らしい花が並んでいます。これから先、野山は花の端境期を迎えますが、気をつけて歩けばまだまだたくさん出会えます。
| 湿地 |
昭和40年代くらいまではこの辺りでもこんな風景があちこちで見られたのでしょう。今ではこの林の向こうは市街地です。
| エゴノキの花 |
歩道のいたるところにエゴノキの白い花が散っていました。花冠ごと落ちているのでよく目立ちます。
| 昼食 |
12時10分。カキノキの下で昼食にしました。今年も木陰を求める季節になったのです。ついこのまえまで花粉に悩まされていたのに。
去年一年間、二十四節気とともに季節の移ろいを見つめてみて、その微妙な移り変わり方にあらためて気づかされたのですが、そういうことでもしない限り気がついたらもう夏、いつのまにか秋、といったふうなことになってしまいます。もったいないですね。
| クワの実 | シマヘビ |
30分ほど休憩して、再びぶらぶらと歩き始めます。
小さな池のほとりにクワの実が赤く色づいていました。でもまだ食べ頃ではありません。もっともっと赤黒く熟さなければ。
そのクワの枝が池の上に張りだしているその先にシマヘビがくつろいでいました。葉陰ということもさることながら、池の上を渡ってくる風が涼しく、休憩にはもってこいなのかもしれません。
| エゴノキ |
それにしてものんびりとした楽しい観察会です。肩肘を張らないこの雰囲気がなんともいえずyamanekoには心地よい。
柿沼さんは奥さんとこの観察会を主催されているようで、ここ生田緑地では奇数月に開催しているのだとか。偶数月は目黒だとのことなので、きっと自然教育園とか林試の森とかその辺りで行われているのかもしれません。(聞くのを忘れていました。)
| 枡形山展望台へ |
道は小山の斜面を上りはじめ、やがて稜線部に出ました。ここは専修大学との境にある西門からすぐの場所で、舗装道路で人通りも多いです。
ここからは稜線部をほぼ水平に移動して行きます。途中から枡形山展望台を目指してまた土の小道に入りますが、これまでの谷筋とは違って乾燥した環境です。
| 展望台前の広場 |
展望台のある広場は完全な都市型公園になっていました。シートに座ってお弁当を広げている人やバドミントンをしている人など、のどかな風景です。
さっそく展望台に上がってみることにしました。
| 展望台からの眺め(北方向) |
枡形山の標高はわずか84m。展望台の高さが10数mあるとして、アイポイントとしては約100mくらいでしょうか。上の写真は真北の展望。多摩川の緑がわずかに見えていますが、見渡す限りの市街地です。その向こうは調布の辺りになります。写真のずっと右手(写っていませんが)には新宿の高層ビル群もはっきりと確認できました。
午後2時20分、生田緑地のメインゲートである東口に下りてきました。
ふくらはぎには心地よい疲労が感じられます。柿沼さんから最後のまとめがあって、解散となりました。誰一人けがをすることもなく、無事終了しました。ありがとうございました。
すばらしい晴天の下での観察会。こんな楽しい観察会ならまた参加してみたいと思います。
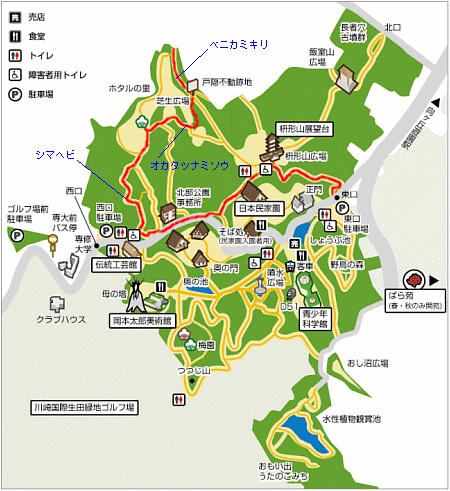 |
生田緑地ホームページ(川崎市)から |