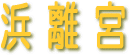
浜離宮 〜三百年の時を超えて〜
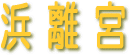 |
【東京都 港区 平成21年3月7日(土)】
3月に入ってからずっとぐずついた天気の日が続いています。したがって毎日肌寒いです。早くも「菜種梅雨」か?
土曜の朝、徹夜明けで帰宅するときはどんよりと曇って風も冷たかったのですが、一眠りして起きてみると久々に晴れているではありませんか。時計を見ると午後1時過ぎ。ちょっくら気分転換に出かけてみるか。
ということで、今日は汐留にある浜離宮庭園に行ってみることにしました。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
新宿、四ッ谷、赤坂、新橋とドリーム号を走らせ、目的地周辺でナビで駐車場を検索。何回か交差点を曲がるうちに、なんといつのまにか首都高に入ってしまうというアクシデント。やむなく芝公園ランプまで都心環状線を走って行くことになってしまいました。
あらためてナビに従い最寄りの駐車場へ。今度はどこをどう間違ったのか日テレの駐車場に入ってしまい、あえなく退場。ようやくその隣にあるロイヤルパークホテルの地下駐車場に滑り込んだのは3時を回っていました。(ホテルはもとより駐車場も立派だったのですが、料金も30分300円と立派でした。)
| 庭園入口 |
ずいぶん久しぶり。前回来たのは平成の始めの頃だったと思います。懐かしいというよりもうすっかり忘れてしまっています。
ざっと眺めてみて来園者で目立つのは外国人。純和風の庭園なので、彼らにとっては「日本らしい風景」なのでしょう。あとカップルですか。いかにも見合いの流れで来た、みたいな雰囲気の二人組もあちこちに。まあ、そんなちょっと落ち着いた感じの庭園なのです。
| 振り返ると |
でもそこはそれ、やっぱり都心のど真ん中なので、振り返るとこんな風景です。右は電通、左はソフトバンク、真ん中奥はロイヤルパークタワーです。
| ボケ |
春が近いですね。園内に入って最初に春を感じたのはこのボケの花。なんだかこの花のまわりだけポッと暖かいような感じがします。
| 「三百年の松」 |
この浜離宮、もともと江戸時代の初め頃には将軍家の鷹狩り場だったのだとか。その後甲府藩の下屋敷となった後、6代将軍家宣により将軍家の別邸として整備されたのだそうです。明治になってからは宮内省の管轄となり、戦後東京都に移管されて都立公園となったとのことです。写真の「三百年の松」は、家宣が庭園を整備したときに植えられたものと伝えられています。若い頃はまっすぐだったのでしょうが、長い年月を経て今ではしだれ桜のようになっています。
| お花畑 |
春の風景といえばこれ、菜の花畑。yamanekoの好きな風景で、新婚時代に菜の花を見に行ったりして想い出のある風景でもあります。そういえば通勤の車窓から見える新宿御苑の裏(フェンスと線路との間)に菜の花の土手がありますが、そこもそろそろ真っ黄色に染まる頃だと思います(このところ毎朝、ぼーっとしていて、どんな状態かよく覚えていないのですが。)。ちょうど千駄ヶ谷駅のホームの前です。
| オオイヌノフグリ |
「野山歩き」には、毎年、春になると必ずこの花が登場しますね。それだけ身近で親しみやすい「春の使者」なのだと思います。
| 庚申堂跡 |
園内にはこんな野趣あふれるところも。パンフレットには「庚申堂があったところ」と記されていました。
| 三百年の彼岸 |
運河に面したところにある「新樋の口山」という小山の上からの眺めです。今では埋め立てが進み水産会社の保冷倉庫が建ち並んでいますが、江戸時代には障害物のない東京湾が広がっていたのだと思います。3百年の時を超えて徳川の将軍がこの小山に立ったなら、レインボーブリッジを見て何と言葉を洩らしたでしょうか。
「樋の口」とは水門のことで、造園当初から、ここから園内に海水を取り込み、潮の満ち干で変化する風景を楽しめるように造られていたのだそうです。この小山のふもとには「将軍お上がり場」というところがあり、往時、お殿様ご一行は船で園内に入ったのでしょう。優雅ですね。
| 御亭山 |
新樋の口山のほかにもこんな小山がいくつかありました。ここは「御亭山」と書いて「おちんやま」と読むのだそうです。
| 横堀 |
運河の向こうは晴海、勝どき界隈。最近高層タワーマンションがどんどん建っているエリアです。
| タネツケバナ |
タネツケバナはまだどれも開花前。もうちょっと暖かくならないと開かないでしょう。花の名前は「種付け花」ではなく「種漬け花」。イネの種籾を水に漬ける頃に開花することからこの名前が付いたとのことです。春らしい名前ですね。
| 中島の御茶屋 |
大泉水の真ん中に浮かぶ御茶屋。畔から3つの橋でつながっています。手前の風景は3百年の間ほとんど変わっていないでしょうが、その背後の高層ビルはここ2、30年くらいでニョキニョキと立ち上がってきたもので、時間を飛び越えた何か不思議な気持ちになる風景です。
| ヒドリガモ |
カモものんびりと過ごしていました。
| イヌビワ |
ビワというよりイチジクの風情。それもそのはず、イヌビワはクワ科イチジク属だから。筆先のように尖った冬芽は葉になる芽です。
そういえば最近イチジクって見かけませんね、店先でも。きっと皮をむくときに手が汚れたりするのが敬遠されるのでしょう。いつかミカン農家の方から、甘夏柑のように皮がむきにくく手が果汁で汚れる果物は売れなくなってきた、という話を聞いたことがあります。
| トウカエデの大木 |
トウカエデってこんなに大きくなるんですね。ここまでものは初めて見た気がします。それこそ江戸時代からのものでしょう。老木だからか、トウカエデ特有の鱗片状の木肌がかなりなめらかになっていました。
| アマナ |
そのトウカエデの根元、張り出した根に守られるように咲いていたのがアマナです。夕刻が近づき日射しが陰ってきたので開いてはいませんが、この方が慎ましやかで、今の季節には似合っていますね。
| アオキ |
アオキの花芽が広がりつつありました。硬く締まっていた冬芽が、まさにほころんでいます。
| サンシュユ |
サンシュユも江戸時代に中国から渡ってきたもの。もちろんこの木が当時からあるものではないでしょうが、ときの将軍たちも外来のめずらしい花として、この花を愛でたのかもしれません。
今日はわずかな時間でしたが、久しぶりに浜離宮を散策しました。ここは、息子が幼稚園の散歩でこの庭園に来ていて誤って池に転がり落ちたという、我が家にとってはいまだに語り継がれる想い出の場所でもあります。その息子もすでに成人。身の回りの時間はあっという間に過ぎていきますが、3百年の時を超えて江戸時代の風情を保っているこの庭園は、これからも百年一日のごとくここにあり続けることと思います。
やがて息子が結婚し、その子どもをここに連れてきて自分が池に落ちたことを話してあげる日がくるでしょうか。(息子が話したがらなくても、yamanekoが孫を連れてきて話してやろうと思っています。)