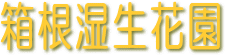
箱根湿生花園 〜秋の野山を詰め込んだ箱庭〜
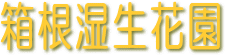 |
【神奈川県 箱根町 平成30年9月10日(月)】
あの永遠に続くのではないかとも思えた酷暑がいつの間にか和らぎ、頭上から降り注いでいた蝉の声も足元からの虫の声に変わりました。やはり季節は少しずつ移ろっているようです。
そこで、むしろこちらから秋の気配を迎えに行こうと箱根の湿生花園に行ってみました。この植物園には過去に何回か行ったことがありますが、この季節に訪れるのは初めてです。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
午前9時、薄曇りの空の下、スタートです。相模原愛川ICから圏央道に乗り、海老名JTCで東名高速の下り線へ。しばらく西進すると、大井松田IC辺りから富士山が大きく見えるようになります。
御殿場ICで高速を下り、国道138号線で乙女峠を越えて箱根エリアに入ります。天気は相変わらずどんよりしていて、予報では2時頃からは雨が降り出すとのこと。なんとか持ってくれれば良いのですが。
| 箱根湿生花園 |
10時40分、現地到着。湿生花園は箱根のカルデラの中、芦ノ湖の北側に広がる仙石原地区にあります。平日ということもあり、駐車場は空いていました。
この湿生花園、じっくり見ようと思えば1日では足りません。ざっと見ても相当な数の植物に出会うことができます。今回は目にとまった植物をサクサク紹介していきましょう。
| ハナトラノオ |
まずはエントランスエリア。
ハナトラノオは北米原産で日本には園芸用として入ってきたもののようですが、野山で野生化しているものを見たこともあります。
| アメリカミズアオイ |
アメリカミズアオイ。こちらも北米原産で既に日本の湖沼に帰化しているのだそうです。
| スイレン |
スイレンは水面の高さに花を付けるのかと思いきや、若干上に出て咲くんですね。水面にも鏡みたく映っています。そういえばハスもそうだったような。
| ウラハグサ |
こんな目立たない植物にもちゃんとウラハグサという名前がある。研究者もいるんでしょうね。
| サギソウ |
サギソウの花冠を鳥が飛んでいる姿に例えるならば、サギというよりツル。サギは首を折りたたんで飛ぶんですよね。
| ホソバシュロソウ |
落葉広葉樹林エリアへ。
ホソバシュロソウの花被片は葡萄茶色。花の色としては珍しい方です。
| ツリバナ |
ツリバナの実がモビールみたいにぶら下がっていました。
| ヤマホトトギス |
ホトトギス三態。花被片が漏斗状に上向きなのがホトトギス、プロペラ状に水平なのがヤマジノホトトギス、タートルネック状に下向きなのがヤマホトトギス。
| ジャコウソウ |
ジャコウソウの名は、茎葉をゆすると麝香(ムスク)のような良い香りがすると言われていることから。そんな良い香りがしていたっけ?
| レンゲショウマ |
レンゲショウマの残り花。花冠を落とし、子房が少し膨らんだものが後ろに写っていますね。
| ツチアケビ |
林の奥にサツマイモが鈴生りに?いやこれはツチアケビの実。大きさはせいぜい10cmほどで、サツマイモと比べてかなり小さめです。ちなみにラン科の腐生植物です。
| サワヒヨドリ |
オミナエシ |
ススキ草原エリアにやって来ました。
サワヒヨドリとオミナエシ。いずれも明るい草地を好む花です。
| コバギボウシ |
コバギボウシはやや湿ったところに生える花。
| シロヨメナ |
シロヨメナは林の縁などでよく見かけます。
| キセワタ |
キセワタ。花冠の上に白い毛が多く、綿を乗せたように見えるので「着せ綿」なのだそうです。だったら「乗せ綿」じゃないのか。
| ゲンノショウコ |
ゲンノショウコは「現の証拠」。下痢止め効能があって、飲むとすぐに薬効が現れることからの名前だそうです。
| カリガネソウ |
かなり独特の姿をしているカリガネソウ。長い雄しべと雌しべが花冠上部からしなった釣り竿のように伸び出しています。この姿を雁が飛ぶ姿に見立てたというのですが、うーむ。
低層湿原エリアへ。
| ミズアオイ |
ミズアオイは水田など水がひたひたしているような環境に生えます。古くは「菜葱(なぎ)」と呼ばれ、葉を食用としていたそうです。
| アキギリ |
キバナアキギリの方は秋になるとよく見かけるのですが、本家(?)アキギリは野生では見たことがありません。それもそのはず、キバナの方は本州以南に広く分布するのに対し、アキギリは中部地方から近畿地方までと分布が限られているからです。
| スズムシバナ |
シロバナスズムシバナ |
近畿地方以西に分布するスズムシバナ。シロバナのものも同種です。今から20年近く前、広島の山間にこの花の自生地があり、何度か見に行ったことがあります。
| ツリフネソウ |
湿った山野での定番、ツリフネソウ。熟した実を触るとはじけるように種子をまき散らすので、自然観察会などで見つけると外せない観察素材です。
ヌマガヤ草原エリアへ。
仙石原名物のススキ原(山腹の白っぽいところ)。今はまだ青々としていますね。
| ヒガンバナ |
ヒヨドリバナに アサギマダラ |
ヒガンバナ、秋ですな。
ヒヨドリバナにアサギマダラが訪れていました。この組み合わせは定番です。ときには1000km以上もの旅をするアサギマダラにとって、ヒヨドリバナの蜜は欠かせないエネルギー源なんでしょうね。羽を優雅に開いたり閉じたりさせながら、小さな花に次々と吻を差入れ食事を取っていました。
| アサマフウロ |
アサマフウロ。フウロソウの仲間は子どもが絵に描くような花の姿をしています。
| エゾリンドウ |
エゾリンドウはエゾといいつつ中部地方以北に分布しているそうです。今は日差しがないので残念ながらみな閉じていますね。
| サワギキョウ |
涼しげなサワギキョウ。花冠はキキョウとはずいぶん異なる形態をしていますが、蕾を見るとキキョウとの共通点を感じられます。
| キバナアキギリ |
林の中に入るとキバナアキギリ。形や大きさはさきほどのアキギリと同じです。
森の中の岩場植物エリアにやって来ました。
| ナツハゼ |
やや紅葉が始まった感じのナツハゼ。実が色づき始めています。赤黒く熟した実はおいしい果実酒にすることができます。広島の観察会仲間のTさんがよく作っていたのを思い出すなあ。
| センジュガンピ |
じつはセンジュガンピを初めて見たのはこの場所でした。こんな花があるのかと印象深かったです。
| キレンゲショウマ |
キレンゲショウマ。「天涯の花」として有名ですね。
| アキチョウジ |
アキチョウジもよく見ると不思議な形をしています。訪れた虫は蜜に到達できるんでしょうか。
| シラヒゲソウ |
おお、久しぶりに見たぞ、シラヒゲソウ。初めて見たのは八幡高原でした。人でも花でも初対面のときのことを長く覚えていることってありますね。
| キイジョウロウホトトギス |
紀伊上臈杜鵑草。和歌山県に分布するジョウロウホトトギスです。岩場からしな垂れるように伸び、鶏卵大の蕾を付けていました。
| ホツツジ |
高山エリアへ。
ホツツジは名前のとおりツツジの仲間。そうは見えませんが。有毒植物です。
| マツムシソウ |
マツムシソウは高原の花。これぞ秋の花の代表選手です。
| エゾノキリンソウ |
エゾノキリンソウは北海道からカムチャツカにかけて分布するのだとか。よくぞここ南関東で生きていられるものです。今年の夏は特に暑かったのに。
| ツルビランジ |
他の植物の葉陰に隠れるようにして咲いていたツルビランジ。名のとおりツル性で、岩場からぶら下がるようにして咲くそうです。初めて見ました。
| アケボノソウ |
園の西端にある高層湿原エリアにやって来ました。
花弁に星々を乗せているアケボノソウ。暁の明星なんでしょうね、きっと。
| ハッカ? |
これはハッカかな。ちょっと花序が密集しすぎているようにも見えますが。
| サクラタデ |
サクラタデはタデの仲間内でも一つ一つの花が大きいのが特徴。肉眼での鑑賞に十分耐えます。
| ヒメシロネ |
この辺りから仙石原湿原エリアです。
ヒメシロネは葉腋に小さな花を数個ずつ付けます。シロネに比べて葉が細いことが特徴。
| ノブドウ |
湿原内の灌木にノブドウが絡んでいました。色づきはこれからですね。
| タチシオデ |
タチシオデの実はこれから黒く熟していきます。少し粉をまぶしたようなマットな感じの黒です。
| タカクマヒキオコシ |
シソの仲間、タカクマヒキオコシ。ヒキオコシの名は、昔、弘法大師が旅に倒れた人にこの草を煎じて飲ませたところ元気に立ち上がった、すなわち倒れた人でも引き起こす薬効があるということだそうです。タカクマは鹿児島の高隈山のことでしょうか。
| ヒツジグサ |
未の刻に花開くというヒツジグサ。時刻は午後1時。未の刻とは午後1時から3時までなので、確かにそのとおりでした。さっきのハスとは異なり、水面に浮かぶように花を咲かせるんですね。
最後は湿生林エリアです。
| キツリフネ |
キツリフネは距(尻尾みたいな部分)が巻かないのが特徴。一方、ツリフネソウの距はカメレオンの尻尾みたいに巻きます。
| サラシナショウマ |
サラシナショウマの花序は大きな試験管ブラシのよう。
園内を巡ること3時間。エントランスエリアに戻ってきました。広々とした園に秋の野山をぎゅっと詰め込んだ箱庭のようでした(箱根の庭園だけに!)。ざっと歩いた感じなんですが、十分に堪能でき、満足満足です。
さて、お昼もとうに過ぎ、お腹もすいているので昼食を食べに行きたいと思います(確か園の駐車場脇にお店があったはず。)。その後は、箱根なのでやっぱり温泉ですかね。