
多摩丘陵でフットパス 〜番外編 10年後の相原〜
 |
番外編 「10年後の相原」 |
【東京都 町田市 令和7年9月14日(日)】
9月になれば少しは季節の変化を感じられるかと思ったりしていましたが、そんな期待は簡単に打ち砕かれ、日々酷暑の中で過ごしています。
今回の野山歩きは、10年前にフットパスのコースを歩いた町田市相原地区で。その時とは若干ルートは異なりますが、10年前にも歩いたこの地で、その間の自然の変化などが見られるかもしれません(変わっていないかもしれませんが)。
ところで、なんで久しぶりにこのフットパスを歩こうと思ったのかですが、それは某自然団体の観察会が当地で行われ、それに参加することにしたから。つまりそれをyamanekoが個人的にフットパスと結びつけているだけです。
※ 例によってこのサイト内の記述はyamanekoが感じたり理解した内容に基づいたものであって、もしこのページの記述に誤りがあってもそれは講師の解説が誤っていたということではなく、yamanekoが正しく理解していない公算が大であることをお断りしておきます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| JR相原駅西口 |
午前9時45分、相原駅西口で受付開始。この日の参加者は20人ほどでした。yamanekoは家が近いから普通に起きて支度して来れましたが、遠方から参加している人はなかなか大変だったのでは。新宿からでも1時間くらいはかかりますから。
| 駅前ロータリー |
閑散とした、いや閑静な駅前ロータリー。遠くに丹沢の山並みも望めます。この駅で下車して乗り換える神奈中バスもありますが、やっぱり自家用車で迎えに来る方も多いのでしょう。駐車場も充実していました。
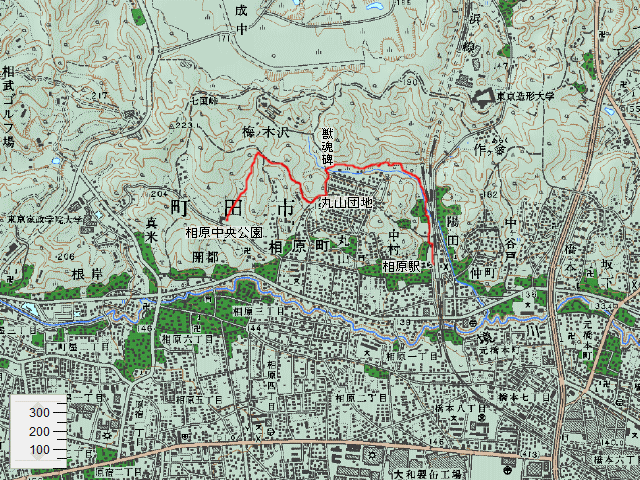 |
Kashmir3D |
今日のルートは、JR相原駅から横浜線の線路を横に見ながら北上。山に突き当たる手前で支谷戸に入り、畑の跡地を通って山際を進みます。そこから丸山団地の外周を巻くように進み、途中から山の中の小道へ。最後は相原中央公園の芝生広場に下りていきます。
| カラスウリ |
最初に目についたのはカラスウリの果実。この時期は「瓜」の名に違わぬ姿をしています。やがて秋が深まると朱色一色になり、最後は乾燥して茶色に変わっていきます。ちなみにスズメウりという植物もあり、こちらの果実は飴玉サイズの球形。カラスウリは「おはぎ」サイズです(そういえば秋の彼岸も近いです。)。
| マルバルコウ |
民家の脇にアサガオをごく小さくしたような赤い花が。熱帯アメリカ原産のマルバルコウです。江戸時代後期に観賞用として入ってきたものだそうです。花はラッパ状で、蜜はその奥の方にある構造。原産地ではその蜜をゲットしているのはハチドリなんだとか。つまりこの花の受粉は鳥が受け持っているということです。じゃあ、ハチドリのいない日本では誰が受粉を担っているのか。長い吻を持っていて、ハチドリ同様に花の前でホバリングできることが必要で、この要件をクリアできるのはガの中のホウジャク類なのだそうです。
| マルバルコウの葉 |
マルバルコウの葉です。一部虫に喰われていますね。犯人はヨツモンジンガサハムシという甲虫だそう。マルバルコウとしては葉や茎から白い乳液を出して虫に喰われにくくしているのだそうですが、よく見ると葉脈は食べず、その間を狙って食べている様子が見て取れます。乳液を避けた結果でしょうか。
ところで、「マルバ」と名前に付けるほど葉が丸いとも思えませんが、これは同じ熱帯アメリカ原産で日本にやって来たルコウソウというものがあり、それに比べると丸っこいということのようです。ルコウソウの葉は身を食べきった後の魚の骨みたいになっています。
| ハキダメギク |
これも熱帯アメリカ原産のハキダメギク。大正年間に東京の世田谷で最初に認められたとのことです。その場所が掃きだめ(ゴミ溜め場)だったことから、この有難くない名を付けられたのだそうです。ただ、名に反して可憐な姿をしていますね。頭花のサイズこそ8mm程度と小さいですが、亀の手のような形の舌状花がポップで、十分に鑑賞に堪えうる可愛いさです。
| チュウゴクアミガサハゴロモ |
今年、爆発的に発生していたこの綿毛のようなもの。植物の茎にびっしりと付いている様子はちょっと鳥肌が出そうでした。これはチュウゴクアミガサハゴロモの幼虫です。右の写真が成虫で、一見ガのようにも見えますが、どちらかといえばカメムシに近い昆虫だそうです。名前のとおり中国原産で、2017年頃から国内で見られるようになったものだそうです。年2回発生し、卵で越冬すると考えられているそう。今年はわが家のバルコニーでも成虫を頻繁に見かけますが、ひょっとしてうちで生まれたものが来年また発生するということになるのでしょうか。(やめてほしい)
住宅と畑の間を歩いていきます。写真の右側に見切れていますがJR横浜線が通っています。
しばらくして線路沿いを離れ支谷戸に入っていきました。左手の水路には水が流れていましたが、10日前の下見の際には完全に干上がっていたそうです。本番までの間に何回か雨が降ったので流れを取り戻したのでしょう。
| ナガコガネグモ |
ナガコガネグモが獲物をぐるぐる巻きにしているところに出会いました。自ら背面の体制にぶら下がりながら器用に獲物に糸を巻き付けていました。
| ゲンノショウコ |
紅白のゲンノショウコです。東日本では白色のものが、西日本では紅色のものが多いとされています。こうやって二つ並んでいるところはあまり見かけません。
ゲンノショウコは消化器系の民間薬として有名ですね。みるみるうちに効いてくるということから「その効果はみたとおり」→「現の証拠」と呼ばれたのが名の由来。
なんだか枯れてボロボロになった立木が。これはナラ枯れしたコナラの木でした。「ナラ枯れ」とは、カシノナガキクイムシという虫が媒介する菌類(ナラ菌)が引き起こす伝染病により一定範囲の木が枯れてしまう現象。yamanekoはてっきり虫に喰い荒らされることで枯れるのかと思っていたのですが、実は菌類による感染症だったんですね。東京で初めて被害が確認されたのは2019年のことで、多摩丘陵では翌2020年のことだったそう。案外最近のことだったんですね。前に住んでいた広島では松くい虫による松枯れがかなり前から問題になっていたので、ナラ枯れも昔からのことだと思っていました。ちなみに、松枯れはマツノマダラカミキリが媒介するマツノザイセンチュウという線虫が木の細胞を喰い荒らし枯らすというものでした。
枯れて剥がれ落ちた樹皮がありました。内側にウネウネとなにかが這いまわったような痕が見られます。これはカシノナガキクイムシが材と樹皮の間に坑道を掘るようにして組織を食べながら縦横に移動した痕跡です。まずオスがトンネルを掘ってそこにメスを呼ぶのだそうですが、メスの背中には小さな窪みがあって、そこにナラ菌が付いているのだそう。結果、メスがトンネルを進むにつれてナラ菌を付けて回ることになるのだそうです。そしてその菌が分解したものが導管に詰まるなどして木を枯らすそうですが、一方、木の方も防御反応で樹脂成分を出し、これがまた導管に詰まって枯死を早めたりするのだそうです。
| ウチワタケ |
ナラ枯れしたものかは分かりませんが、倒れたコナラの幹にウチワタケがたくさん生えていました。確かに団扇みたいです。このキノコはブナ科の枯木に付いて材を分解するのだそうです。講師の方の解説によると、樹木の細胞壁の主成分はセルロースで、セルロースはブドウ糖がたくさん結合したもので非常に分解されにくいのだそう。故に木は硬いということ。キノコはそのセルロースを分解できるのだそうです。
| 凝視が必要 |
ウチワタケの裏側をよーく見てみると、ごくごく小さな穴が空いているのが分かります。それもびっしりと隙間なく。この穴は深い管状になっていて、その管の内側に胞子を作るのだとか。つまり表面積を大きくして胞子をたくさん作れるような構造ということになります。シイタケだったら管状ではなく襞状になっていますね。
山際に沿って歩いていきます。9月も半ばになろうかというのに、まだまだ暑いです。
| ガラニチカセージ |
サルビアの仲間、ガラニチカセージ。この時期、民家の庭先でよく見かける花です。そこにクマバチが来ていました。キバナアキギリに代表されるようにサルビアの仲間は手の込んだ方法で花粉を媒介者に付ける仕組みを持っているものが多いです。
花冠を1個取らせてもらって(下見の際に所有者の方にお断りしてある由)、その構造を見てみると、大きく口を開けたような形の唇形花です。下唇は花粉媒介者(ハナバチなど)の足場の役割を果たしていて、ここに乗って頭を蜜のある花冠の奥に突っ込みます。一方、上唇は長い袋状になっていてその下側に空いているスリットから弓状の雌しべが飛び出しています。雄しべはどこにあるかというと袋状の上唇の中。ハナバチなどがぐっと奥まで体を入れるとシーソーの原理でスリットから雄しべが出てきて虫の背中に花粉の付いた葯を押し付けるという仕組みです。普段は葯を隠しておくことによって、花粉を食べられるリスクを回避しているのです。
右の写真は上唇と下唇をばらしたところ。手前のものが下唇で(奥が上唇)、長い雄しべの先に葯が付いているのが分かります。その雄しべの根元側3分の1辺りのところが下唇にくっついていて、そこがシーソーの支点になっています。ハナバチがもぐり込みその支点の先の部分を押し上げると支点を軸に葯が下りてくるというわけです。
と、まあ、こんなメカニカルな仕組みを用意しているガラニチカセージですが、上のクマバチの写真を見てみると、花冠の正面からアプローチしていなくて、明らかに花冠の根元の萼に取り付いています。なんと、これは萼を切り裂いて、中の蜜を直接吸っているところ。この掟破りな行動は「盗蜜」と呼ばれているそうです。クマバチとしては口が短く花筒の中まで届かないのでこうするしかないのですが、花にとっては大迷惑ですね。
| タマムシ |
先ほどからタマムシの鮮やかな翅が落ちているのを何個も見かけていましたが、生きている個体が参加者の肩に止まってじっとしていたので、写真を撮らせてもらいました。見る角度で色合いが変わるメタリックカラー。これは構造色といわれるもので、翅の色素がこのような色をしているのではなく、翅表面の微細な構造で光の干渉が起こり、それによって目に映るものなのだそうです。
それにしても生きている死んでいるを別にして、この場所にはたくさんのタマムシがいるようです。タマムシは枯れそうな木に卵を産みつけるとのこと。ナラ枯れとの関係があるのでしょうか。
11時40分、しばし休憩で給水タイムです。
| アオバハゴロモ |
先ほどチュウゴクアミガサハゴロモを観察しましたが、こちらは在来のアオバハゴロモ。枝の上部にいる白いものが幼虫。下の方にいる翡翠色のものが成虫です。チュウゴクアミガサハゴロモの成虫はどちらかという翅を開いて止まりますが、アオバハゴロモは合掌のように閉じています。
| クロウリハムシ |
カラスウリの葉がU字型に喰われています。これはクロウリハムシの仕業。U字の内側の部分は欠損していますが、そうなる前の状況はU字型に葉の表面だけ薄くかじって溝を作り、内側と外側を区画した状態になっています。カラスウリは食べられまいとして忌避物質を出すそうですが、それがこの溝でブロックされるのだそう。山でときどき見かける防火帯のような役割ですね。クロウリハムシは安心して溝の内側を食べられるというわけです。これはいったい誰に教えられた技でしょうか。ちなみに、この溝を作る行動を「トレンチ行動」というのだそうです。
| 獣魂碑 |
木の根元に石碑がありました。「獣魂碑」と彫られています。家畜の供養をするものだと思います。
| クズクビボソハムシ |
谷戸を離れて、団地の縁の車道を進みます。
こちらのクズの葉も穴が開いていますね。クズの葉を専門で食べるクズクビボソハムシの食痕だそう。ご本人もいました。この虫は2016年頃、東京都やその近県で確認されるようになったそうで、近年兵庫県でも見つかったそう。ずいぶん離れていますが、船か車で運ばれたのでしょうか。ただ、クズしか食べないこの虫が分布を拡大するということは、卵が付いたクズの葉が運ばれたということでしょう。それはいったいどういうシチュエーションなのか。想像がつきません。
| ノブドウ |
うっすらと色づき始めたノブドウの実。熟しても食べられません。タマバエの幼虫が入り込んで虫えいを作っているものも多いそうです。
| どんぐりに空けられた穴 |
地面のあちこちにコナラの枝先が落ちていました。大体が1個のどんぐりと数個の葉が付いている状態です。これはハイイロチョッキリという甲虫がわざわざ切り落としたものだそう。よく見ると殻斗(帽子の部分)に小さな黒点が。これはハイイロチョッキリが空けた穴で、どんぐりの中まで深く穴を空け、卵を産みつけた痕。その後、枝を噛み切って地面に落とすのだそうです。中の卵から孵化した幼虫は、どんぐりの内部を食べて育ち、その後地中に移動するのだそう。そのためにも空中にあるより地面に落とした方が良いということなのかもしれません。葉を残すのは着地時の衝撃を和らげるためか。
ところで、この穴。必ず殻斗の部分に空けられていて、果実本体の部分に空けられたものは見かけません。皮が硬いからではないかとも聞いたことがありますが、写真のように殻斗と本体をずらしてみると、穴は殻斗も皮も貫通して掘り進んでいることが分かります。ただ、殻斗に覆われていた部分は若干色も薄く、日に当たっている部分に比べると柔らかいのかもしれません。他にも、本体はツルツルしていて足掛かりがないからではとか、空けた穴を塞ぐ部材として殻斗の繊維を使うからではないかとか、いろいろあるようです。
| エゴノキタケ |
まるでサンゴのような形をしているキノコ。エゴノキタケです。ということは生えているこの枝はエゴノキということですね。見えている部分はシイタケで言うと裏側の襞の部分に当たります。
ところで、キノコが「生える」という表現はどうも実態に即していないようです。キノコの本体はカビ状の菌糸で、普段の状態は地中や木の内部に薄く広がっているというもの。それが気温とか湿度とか一定の条件が揃うと菌糸が変形しむくむくと子実体(いわゆるキノコ)を作るのだそうです。その際の条件とはすなわち胞子を飛ばして定着しやすい状況のことなんでしょうね。(めんどくさいので引き続き「生える」でいきますが。)
山道に入りました。住宅地からそんなには離れていませんが、案外うっそうとしています。
| キクバナイグチ |
なにやらヒョウ柄のようなキノコがありました。キクバナイグチという菌根菌だそうです。講師の方によると、菌根菌とは「菌根を作って植物などと共生するキノコ(菌類)」のことだそうで、菌根とは、植物の根に菌類が侵入し、両者でやり取りが行われる仕組みのこと。植物から菌類へは光合成で作った糖類などが提供され、菌類から植物へは土壌内の窒素やリン、水などが供給されるという共生構造のことなのだそうです。この写真のキクバナイグチは菌根を作っていた菌類の子実体なんですね。
尾根上のやや開けた場所に出ました。分岐になっています。
| シックイタケ |
そこにこんなものが。スギの丸太の切り口にドーナツ状にキノコが生えています。小さな傘がびっしりと並んでいますね。これはシックイタケだそう。漆喰のように奇麗な白色というのが名の由来のようです。近年では漆喰自体に馴染みがない人も多いのでは。建築材料として漆喰が使われることも稀でしょうから。断面しか見えていませんが、材の中には菌糸が広がっていて材を分解しているところでしょうね。キノコが切り口の中心部に生えていないのは、この部分は抗菌性のある樹脂成分が多く、菌糸が広がりにくいからではないかということです。
分岐を左に折れて斜面を下っていきます。さっきまでとは違い頭上が抜けた明るい森です。
| ギャップ |
この辺りは2020年頃からのナラ枯れ被害に遭った場所のようでした。その前は密に茂った高木の樹冠から木漏れ日が差し込むといった環境だったそうです。そんな大きな木がナラ枯れで倒れてしまうと、そこには広い空間(「ギャップ」というのだそう)が現れ、十分に日光が差し込むようになります。するとまずはフロンティア植物と呼ばれる拡大力旺盛な植物が入り込み、その後長い時間をかけて元あったような森になるのだそうです。そのような植物にとっては待ちに待ったチャンスということなんでしょうね。
| アキノノゲシ |
アキノノゲシが花を付けていました。花茎が横倒しになってから咲いたのか、頭花が横に並んでいます。本来は直立し、高さが2mくらいになるものもざらで、花は高いところにあるのが普通です。
| ツルタケダマシ |
ツルタケダマシというキノコが生えていました。これも菌根菌なのだそうです。特にブナ科の木の根に付く菌だそうで、辺りを見回してみると確かに5mほど離れたところにクヌギがありました。菌根の様子を観察しようと地面を掘ってみたのですが、残念ながら確認できませんでした。それにしても樹木の根ってずいぶん遠くまで伸びているものなんですね。
この菌根のような植物と菌類の関係は、どうやら特別なものではなく、むしろ草本、木本を通じて多くの植物が菌類とやり取りをしているとのことです。これはちょっと意外でした。その関係を遮断してしまうと、植物の育成が大きく鈍るほど。そうなるとうちの鉢植えなどは関係を結ぶ菌類もいないだろうし、可愛そうな状況なのかもしれません。
| 相原中央公園 |
12時55分、相原中央公園の芝生広場に出ました。この先にある管理棟まで行って観察会は終了です。
今回の野山歩きは、10年前に歩いたフットパスを概ねトレースするようなルートでした。フットパスは自然に触れながらただのんびり歩くだけで十分に楽しいものですが、今回の観察会のように折々で興味深い解説があるとまた違った楽しみも加わります。機会があれば是非また参加したいと思います。
そして10年ぶりに歩いてもう一つ気づいたこと。それは10年の時を経て自分の足腰がそれなりに弱っていたということでした。まあ、これはしょうがないですね。